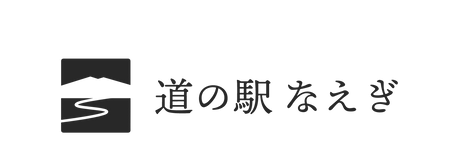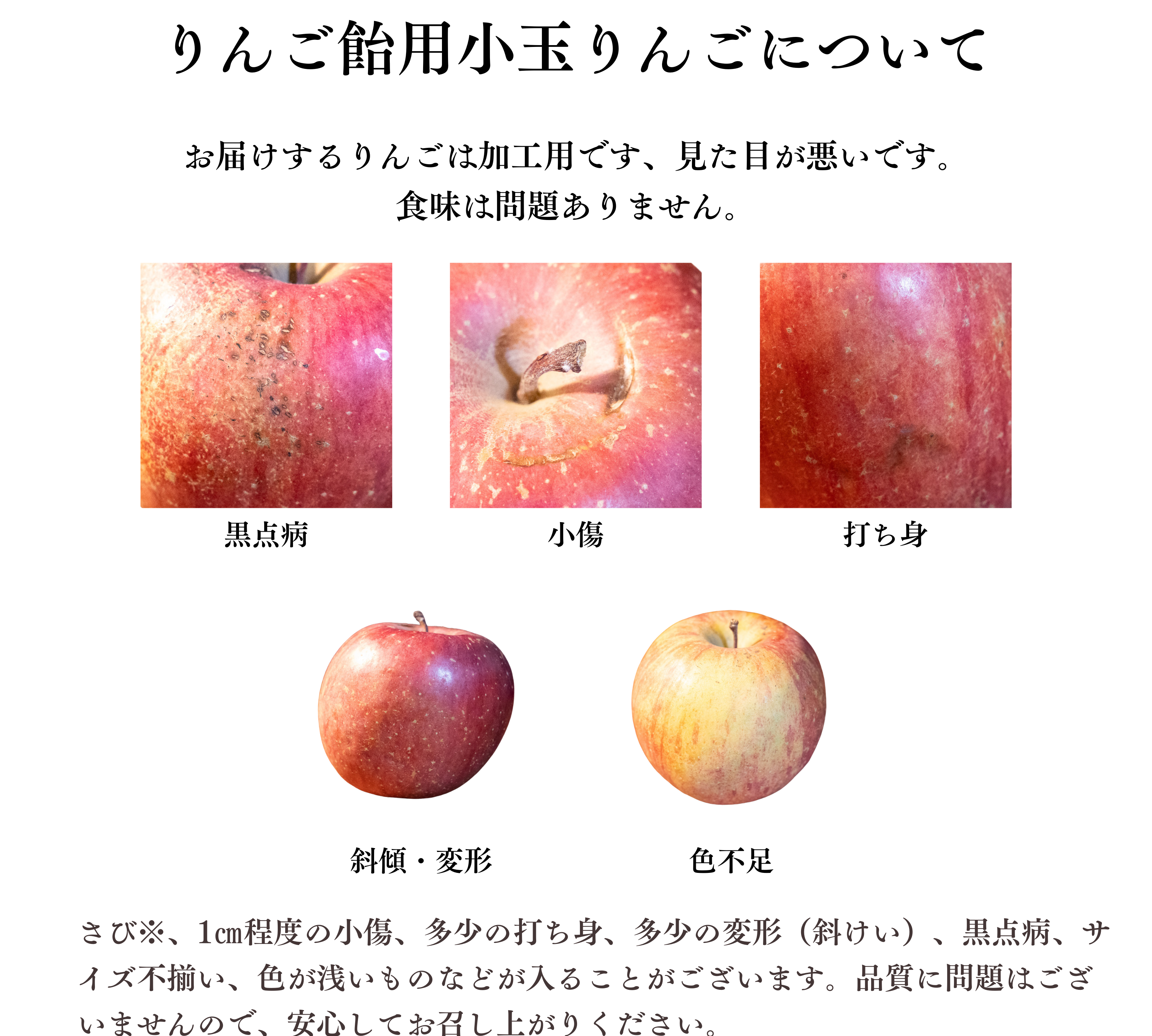希少品種の黄色いりんご「ぐんま名月」とは?
「ぐんま名月」は、近年じわじわと人気を集めている甘みの強い黄色系のりんごです。 市場では、「ふじ」のような主力のりんごが数多く流通しているなか「ぐんま名月」の流通量はりんご全体のわずか0.9%!たいへん希少な品種となっています。いったい、希少性が高い「ぐんま名月」とはどんな品種なのでしょうか。その特徴について解説していきます。 希少な品種といわれる「ぐんま名月」の特徴は? 「ぐんま名月」は「あかぎ」と「ふじ」を交配し育成された群馬県生まれのりんごです。1991年(平成3年)に品種登録されました。果実はやや大きめで約280〜350g。果皮は黄緑色から黄色で、日光が当たった部分が赤く色づく特徴があります。コクのある甘さとやさしい酸味とのバランスの良さが人気の秘訣。果肉はサクッとした食感、香り豊かで果汁も豊富です。 また、「ぐんま名月」は耐病性があり、無袋栽培に適しています。そのため、有袋栽培と比較して十分な太陽の陽ざしを浴びることができ、葉取り作業を行わなくても高い糖度の果実を実らすことができます。 「ぐんま名月」の流通量は本当に少ないの? 黄色系りんごは、赤いりんごに比べてキズやスレなどが目立ちやすく、検品で苦労するため生産者さんがあまり栽培に積極的ではないようです。また、「ぐんま名月」の旬の時期が短いことも流通量が少ない要因かもしれません。しかし、袋がけや葉取り作業を行う必要がないため、青森県では栽培面積が年々増加しており、食味の良さからも知名度が高まっています。 参考資料 袋がけや葉取りがいらない?! 「ぐんま名月」の主な生産地 「ぐんま名月」の栽培面積のトップは青森県です。栽培面積は約172ヘクタールで全国の生産量の半分以上の割合を占めています。続いて長野県、群馬県が主な生産地です。「ぐんま名月」の栽培面積は全国のりんご栽培面積のわずか1%ほどしかありません。そのため非常に希少性の高いりんごといえます。群馬県で栽培された「ぐんま名月」は「群馬名月」、群馬県以外で生産されたものは「名月」や「めいげつ」と区別して呼ばれていることもあります。《令和2年 生産地別栽培面積》 引用元:農林水産省 りんごの生産地 「ぐんま名月」の出回り時期はいつ? 「ぐんま名月」の出回り時期は11月頃です。収穫後も熟成が進むためより食味はより深い味わいに変わっていきます。 おいしい「ぐんま名月」を見分けるコツは? 「ぐんま名月」は縦に長めのものを選ぶとよいでしょう。色は、黄緑から黄色に変わっていると熟した証です。甘みが強いりんごをお好みの場合は赤みの多いりんごを、酸味があるりんごがお好みの場合は黄緑のものを選ぶとことをおすすめします。外観はざらつきがあるものが栄養を多く含み完熟している傾向です。さらに、芳醇な香りとずっしりとした重さを感じたら、それは果汁が豊富に含まれている証拠です。 参照サイト おいしいりんごの見分け方 「ぐんま名月」の保存方法は特別なの? 常温保存も可能ですが、おいしく食べることができる期間は1ヶ月弱程度です。 鮮度の低下を防ぐために、りんごをひとつずつ紙で包み、それらをビニール袋に入れて冷蔵庫で保管していただくと、2ヶ月間ほどおいしくお召し上がりいただけます。その際、エチレンガス対応の保存袋で保存することをおすすめします。 まとめ この記事では、非常においしいと評判の希少品種「ぐんま名月」の特徴を解説しました。数多くのりんごの品種が市場に出回るなか「ぐんま名月」はたいへん希少であり、出荷量はりんご総計のわずか0.9%程度です。「ぐんま名月」を一度購入した消費者の多くは、その後もリピーターになるといわれており人気の高さがうかがえます。このような希少価値の高い「ぐんま名月」をお歳暮や贈答品のトップシーズンにタイミングよく発送することができます! 『道の駅なえぎ』では、生産者から直送で販売しております。是非一度お試しください!...